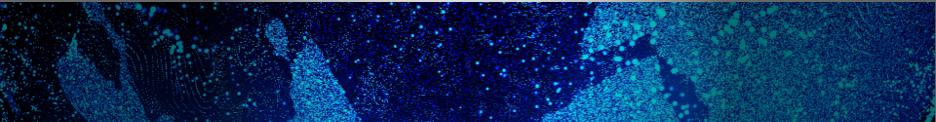国際問題
ニアショアリングは関税問題の万能薬ではない
ニアショアリングが真の経済戦略ではなく、関税回避を目的として行われる場合、それによって解決される問題よりも多くの問題を引き起こす。
![2024年7月8日、中国・浜州市の繊維企業の生産工場で、輸出用の繊維製品の注文を処理する作業員。[NurPhoto/AFP経由]](/gc7/images/2025/10/09/52241-plant-370_237.webp)
Global Watch |
ニアショアリングは今、話題のキーワードだ。企業は生産拠点を本拠地や最終消費地に近い地域へ移しつつあり、表面上は双方にとって好都合のように見える。
サプライチェーンの短縮、輸送コストの削減、関税の悩みも軽減――悪いことなどないように思える。だが少し掘り下げてみると、ニアショアリング、特に関税回避が目的のものは、賢明な経営判断というより短絡的な賭けにすぎないことがわかる。短期的には心地よく感じられるかもしれないが、地域経済や世界経済、そして皮肉にもそれを推進する国々自身にとって、高くつく戦略なのだ。
基本的に、ニアショアリングとは、生産を主要市場に近い国へ移すことを指す。短期的には即効性のある対策だが、長期的な影響を伴う。アジアの企業にとっては、東南アジアやインドへの移転を意味するかもしれないし、南米ではコロンビアやブラジルなど隣国への生産拠点の移動を指す場合もある。
その目的は、コストを削減し、関税を回避し、事業を円滑に進めることにある。素晴らしく聞こえるだろう。しかし、ニアショアリングが真の経済戦略ではなく関税回避を目的として行われる場合、それによって解決される問題よりも多くの問題を引き起こす。
例えばアフリカを見てみよう。エチオピアやケニアのような国々は、中国での生産コスト上昇を避けたい企業にとって魅力的なニアショアリング先となっている。こうした動きが一定の経済活動を促している一方で、多くの場合不安定な外国投資への依存も生み出している。
さらに、強固な現地サプライチェーンが欠如しているため、これらの国々は遠く離れた市場から原材料を輸入せざるを得ず、ニアショアリングによるとされるコスト削減効果を帳消しにしてしまっている。
アフリカでは、ニアショアリングは機会と課題の両方をもたらしている。例えばエチオピアは、かつて中国に依存していた企業を引きつける繊維製造の拠点となった。しかし、この変化には負の側面も伴っている。
経済的不平等
同国のインフラは大規模生産の需要に対応しきれず、輸入原材料への依存がニアショアリングのコスト上の優位性を損なっている。
さらに、アフリカの角地域における政治的不安定は、サプライチェーンの信頼性に大きなリスクをもたらしている。もう一つのニアショアリング拠点であるケニアでは、テクノロジーやサービス産業が成長している。インドや中国の企業がナイロビに拠点を設け、アフリカや中東市場へのサービス提供を行っている。
これによって雇用は生まれたものの、その恩恵は都市部に集中しがちで、農村地域が取り残されるなど、経済的不平等を一層深める結果となっている。
南米では、ブラジルは豊富な労働力と天然資源を背景に、長年にわたり有望なニアショアリング先と見なされてきた。しかし、高い税負担、複雑な規制、そして不十分なインフラが、企業にとって困難な事業環境を生み出している。
ブラジルにニアショアリングした多くの企業は、想定以上のコストや物流の問題に悩まされている。一方、コロンビアは、特にテクノロジーやカスタマーサービス分野において、より現実的なニアショアリング先として台頭している。
インドやロシアの企業が北米および南米市場向けにサービスを提供するため、コロンビアでの事業への投資を進めている。こうした動きはコロンビア経済を活性化させているものの、同時に外国資本への依存を生み出し、世界的な経済変動の影響を強く受けやすい状態にしている。
アジアにおけるニアショアリングの状況は複雑だ。インドは特にテクノロジーや製薬分野で、中国に代わるニアショアリング先としての地位を確立している。ロシアの企業は、両国の強固な政治的・経済的関係を背景に、製造業やITサービスの拠点としてインドを利用するケースが増えている。
しかし、この移行には課題も多い。インドの規制環境は複雑で対応が難しく、インフラも中国や他の先進国と比べて大きく劣っている。その一方で、ベトナムやインドネシアといった東南アジア諸国は、中国への依存を減らしたい企業にとって人気のニアショアリング先となっている。
混乱への脆弱性
これらの国々は低い労働コストと主要市場への近さという利点を持つ。しかし、原材料や部品を中国に依存しているため、中国経済との結びつきは依然として深く、中国のサプライチェーンに生じる混乱の影響を受けやすいという脆弱性を抱えている。
本質的に、関税回避を目的としたニアショアリングは、一種の経済的ナショナリズムである。たとえ世界貿易を混乱させることになっても、自国や自地域を優先するという発想だ。だが皮肉なことに、この種のナショナリズムはしばしば逆効果を招く。短期的な利益に固執するあまり、長年にわたり世界経済の成長を支えてきた自由貿易の原則そのものを損なってしまうのだ。
再びアフリカを見てみよう。ニアショアリングは一定の経済的利益をもたらしたものの、同時に外国投資や海外市場への依存も生み出している。この多様化の欠如が、アフリカ諸国の経済を世界的な景気変動に対してより脆弱なものにしている。
同様に、南米ではニアショアリングに注力するあまり、単一の市場や産業への過度な依存が進み、長期的な経済の安定性が損なわれる傾向がある。解決策はニアショアリングを完全に放棄することではなく、その目的と手法を再考することだ。関税回避の手段としてニアショアリングを利用するのではなく、企業や政府は貿易規制の遵守を、国際的なパートナーシップを強化し、持続的な成長を促すための機会として捉えるべきである。
長期的なレジリエンスの構築
関税はしばしば負担と見なされるが、企業に対して現地経済への投資、サプライチェーンの多様化、そして生産者と消費者の双方に利益をもたらす形でのイノベーションを促すきっかけにもなり得る。例えば、関税を遵守することにより、企業は原材料を現地で調達するようになり、遠隔地の供給元への依存を減らし、地政学的な不安定性に伴うリスクを軽減することができる。
アフリカでは、関税回避だけを目的に拠点を移すのではなく、インフラ整備や人材育成への投資を通じて自立的な製造エコシステムを構築することが望ましい。このような取り組みは、貿易規制に沿うだけでなく、長期的なレジリエンスと経済的自立を育むことにもつながる。
同様に、南米では関税の遵守がテクノロジーや農業といった産業分野でのイノベーションを促進する可能性がある。貿易ルールを守ることで、企業はしばしば遵守を条件として設けられている減税や補助金など、政府の支援策を活用できるようになる。
例えばブラジル政府は、製造業の再活性化を目指した改革を進めており、短期的な対症療法としてのニアショアリングに頼るのではなく、現地生産への投資を選ぶ企業に新たな機会を提供している。
アジアでは、インドやベトナムのような国々が、短期的なコスト削減よりも持続可能な発展を優先する関税遵守型のパートナーシップから利益を得ることができる。貿易協定の枠組みの中で事業を展開することにより、企業は現地サプライヤーとの関係を強化し、品質管理を改善し、責任ある国際的企業としての評価を高めることができる。
このようなアプローチは、サプライチェーンの混乱リスクを低減させるだけでなく、企業を倫理的かつ持続可能な事業運営の先導者として位置づけることにもつながる。
関税回避を目的としたニアショアリングは、一見すると賢明な回避策のように見えるが、実際には地域経済と世界経済の双方に悪影響を及ぼす予期せぬ結果を招くことが多い。一方で、関税を遵守することは、長期的な安定と成長への道を開く手段となる。
それは企業に、現地経済への投資、レジリエントなサプライチェーンの構築、そして関係者すべてに利益をもたらすイノベーションの推進を促すものである。貿易規制を障害ではなく機会として受け入れることで、企業はより均衡の取れた公正な世界経済の実現に貢献することができる。
このアプローチは、競争より協調を、便宜より持続可能性を、短期的な利益より長期的なレジリエンスを優先するものである。最終的に、関税の遵守とは単にルールに従うことではなく、すべての人に利益をもたらす仕組みを築くことであり、世界貿易を分断ではなく共通の繁栄をもたらす力として維持することにほかならない。