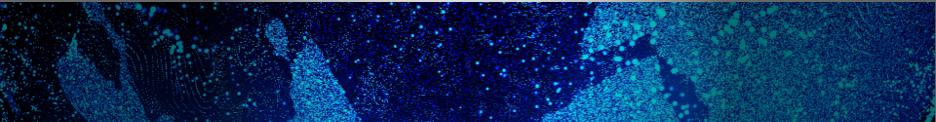新たな課題
新たな冷戦:北極の軍事化
かつては世界的な競争からほとんど影響を受けない凍てつく辺境だった地域が、今や地球上で最も戦略的に争われる地域の一つになりつつある。
![3月27日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が北極圏の港町ムルマンスクで、ロシア海軍の原子力潜水艦「アルハンゲリスク」(885M型ヤーセンM級)を視察した。[Sergei Karpukhin/AFP]](/gc7/images/2025/08/15/51542-russ_sub_arctic-370_237.webp)
Global Watch |
かつては氷に覆われた静寂な不毛の大地だった北極。しかし今、そこにはエンジンの轟音が響き、地政学的緊張が静かに渦巻いている。
衛星画像には、新たに建設された滑走路やレーダードーム、軍事基地が白銀の大地に点在する様子が克明に映し出されている。かつては全球的な競争からほとんど影響を受けていなかった氷に覆われた辺境だったが、今や地球で最も戦略的に争点となっている地域の一つへと急速に変貌しつつある。
その変化の激しさは、北極の風景そのものに匹敵するほど鮮明だ。気候変動の影響で加速する形で、北極の氷はかつて科学者が予想していた以上に急速に融けている。
かつては通行不可能だった北西航路や北方航路などのルートが、年間を通してより長い期間航行可能になりつつある。推計によれば、北極海は2035年までに夏季には氷が消え、世界の貿易と物流を一変させる可能性がある。
船舶会社にとっては、これらの航路がスピードアップとコスト削減をもたらす可能性を秘めている。
永久凍土の下や北極海の海底には、世界の未発見埋蔵量の約13%の石油と、ほぼ30%の天然ガスが存在すると推定されている。また、現代の電子機器やクリーンエネルギー技術に不可欠なレアアースなど、まだ手つかずのまま眠る希少鉱物も豊富に含まれている。
軍事的足跡の拡大
北極に接する国々―ロシア、アメリカ、カナダ、ノルウェー、およびグリーンランドを通じて関与するデンマーク―は、自国の権益を確保するべく、今や激しく競争を繰り広げている。
しかし近年では、条約や科学調査ではなく、軍艦やミサイルシステム、戦略的前線基地によってその存在感を示すようになってきている。
氷が後退するにつれ、国家の領有権と国際水域の境界線はあいまいになりつつあり、各国は必要とあらば武力でその線を引こうと軍備を整えている。
北極地域の戦略的位置は、単なる商業の問題にとどまらない。実際、この地域は核大国間のミサイルの主要ルートともなっており、ロシアとアメリカ間の大陸間弾道ミサイル(ICBM)が最も短距離で通過する航路は、真っ直ぐ北極点の上空を横断する。
早期警戒レーダーシステムや衛星追跡基地、最先端の武器試験場の設置により、北極は次第に軍事化が進む「戦略的高地」となりつつある。そこでは、国家安全保障への懸念が経済的利益への野心と交差している。
北極地域で最も長い国境を持つロシアが、主導権を握り、 極地の景観を要塞化された最前線へと変貌させている。
クレムリンは、コラ半島や北方航路沿いの施設を含む数十か所のソ連時代の基地を改修してきた。
最新鋭のS-400ミサイルシステムが氷に覆われた海岸線を監視し、年間を通じて航路を確保できる原子力砕氷船が北極海を巡回している。極地の氷の下に潜む極超音速兵器搭載可能な潜水艦は、モスクワの軍事的野心の最先端を象徴している。
モスクワは北極を、各国が共有するグローバルな領域ではなく、自国の経済的生命線であり、防衛上の緩衝地帯と見なしている。
ロシア当局は公然と、自国の北極における権益に他国が挑戦する場合には「適切な軍事的措置」で対応すると表明している。こうした姿勢は単なる防衛にとどまらず、新たな貿易航路や資源開発地域に対する支配権の確立を狙ったものだ。
北極における存在感
これに対応して、アメリカおよびNATO諸国も北極における存在感を強めている。アメリカ国防総省は、アラスカやグリーンランドにあった長年休止状態だった冷戦期の軍事施設を再稼働させ、ロシアの進出に対抗するため、北極地域での戦闘訓練や監視活動を活発化させている。
「コールド・レスポンス」や「トライデント・ジャンクチャー」といったNATOの演習は、西側が戦わずして北極圏の支配を譲らないことを示すために実施されている。米軍の2024年北極戦略は、極地における最大の戦略的脅威としてロシアと中国の両国を明確に名指ししている。
中国は地理的に北極圏に接していないが、より巧妙な形でその存在感を示している。中国政府は自らを「準北極国」と称し、極地インフラに巨額の投資を行っている。その一環として、「一帯一路」構想に含まれる「極地シルクロード」を推進し、北極海を通る航路の確保や研究拠点の設立を進めている。欧米の分析当局の一部は、これらの研究施設の中には軍民両用の目的に使われる可能性があるものもあると指摘している。
中国は自国の関心はあくまで科学的・商業的なものだと主張しているが、その存在感の拡大がもたらす戦略的影響は見過ごされてはいない。
北極の軍事化はもはや遠い将来の抽象的な可能性ではなく、現実に進行中の事態である。そこには気候変動、経済的利益への野心、そして変化する国際的な力のバランスが背景にある。
かつては氷と静かな強靱さの地であった場所が、今や世界的な競争の新たな舞台となりつつある──海の冷たさに匹敵するほど高い利害が絡む、静かで凍りついたチェス盤のような場である。