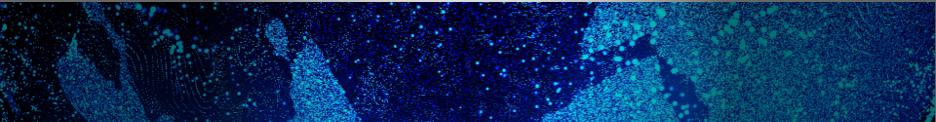国際問題
リチウム争奪戦:南米のグリーンエネルギー繁栄
専門家たちは、倫理的なリチウム採掘には先住民の共同管理や透明性の高い合意形成、堅実な環境保護措置が不可欠だと指摘しています。
![2024年7月4日、アルゼンチン・サルタ州のセロ・セントenario・ラトネス塩湖にあるエラミネ・リチウム採掘プラントで、作業員が鹵水(ろすい)のポンプ施設を点検している。[ルイス・ロバヨ/AFP]](/gc7/images/2025/08/15/51500-lithium-370_237.webp)
Global Watch |
アルゼンチンのサリナス・グランデス。広大な白銀の大地を前に、マリア・キスペさんは何世代にもわたって祖先が歩んできたこの塩湖を静かに見つめる。「ここはただの土地じゃない。記憶であり、アイデンティティそのものよ。なのに今、彼らはそれを奪おうとしているの」と彼女は語る。
マリアは、今回のリチウムをめぐる新たな資源ブームに抵抗する多くの先住民指導者の一人です。リチウムは電気自動車を動かし、再生可能エネルギーへの移行を支える上で不可欠な金属です。
世界が交通機関の電化を進め、二酸化炭素排出量の削減を目指す中、リチウム埋蔵量が世界有数のアルゼンチンとボリビアは、「ホワイトゴールド」と呼ばれるこの資源の採掘を急かされる形で追い詰められています。
しかし、グリーンエネルギーの繁栄には影の側面も伴っている。先住民のコミュニティが追い出され、生態系が干上がっている。その一方で、先住民の声は無視され、あるいは意図的に沈黙させられているのだ。
世界を駆けるリチウム熱狂
「リチウム・トライアングル」―アルゼンチン、ボリビア、チリが接するこの地域は、世界のリチウム供給量の半分以上を占める。自動車メーカーが2025年までに1700万台以上とされる電気自動車の生産目標達成に向け競い合う中、リチウムの需要は急激に高まっている。
このブームの主な恩恵を受けるのは、中国の赣鋒リチウム(ガンフェン・リチウム)のような多国籍企業や、ボリビアの国営企業YLB(リチウム・ボリビア公社)などだ。
政府は外国資本を惹きつけるため、税制優遇措置や許認可の迅速化を提供している―地元の環境や 人権懸念 。
「これは『グリーン・コロニアリズム』です」と環境弁護士のカロリナ・ガルシア氏は指摘する。「資源の対象が石油からリチウムに変わっただけで、構造は同じ。南半球から採掘し、北半球がその恩恵を受けるという植民地型のモデルが今も繰り返されています。」
リチウムを採取するため、鉱山企業は地下の含水層から鹸水(ろすい)をくみ上げ、巨大な蒸発池に流し込む。この工程は、地球上でも特に乾燥した地域で膨大な量の水を消費することになる。
アルゼンチン・フフイ州では、地域住民が飲料水の湧き水が枯れつつあると訴えている。これは伝統的な農業や塩の採取に深刻な影響を及ぼしかねない。
先住民コミュニティによる「自由かつ事前の知情同意(FPIC)」を義務付ける国際的な保護規定があるにもかかわらず、地元住民は多くの鉱山プロジェクトが実質的な協議を経ずに進められてきたと訴えている。
「私たちの地域では、一度もまともな説明や協議が行われたことはありません」とコヤ族の指導者ルーカス・ママニ氏は語る。「政府は、私たちが気づかないうちにすでに探査を許可してしまったのです。」
多くの地域社会には、インフラの整備や雇用、学校の建設が約束されてきた。しかし地元の指導者たちによれば、こうした約束はしばしば実現されず、一方で環境への負荷だけが蓄積しているという。
先住民の間では沈黙を守る動きは広がっていない。アルゼンチンでは、30を上回る先住民族グループが連携し、水と土地の権利を守るための連合を結成した。ボリビアでは、アイマラ族やケチュア族の活動家たちが、中国の鉱山企業との新たな契約に疑問を呈している。
抗議活動に立ち上がった人々は、次第に高いリスクにさらされている。鉱山プロジェクトに反対したことを理由に、嫌がらせや法的脅し、さらには暴力を訴える指導者もいる。一方で、こうした事態に関する報道は依然として極めて限定的だ。
「道路を封鎖しない限り、私たちには声がないのよ」とキスペさんは言う。
未来を築くということ
この闘いは地域にとどまらず、地政学的な次元でも展開されている。アメリカ、中国、欧州連合(EU)はいずれも、戦略的に重要な鉱物の供給を確保するため、南米への影響力獲得を競い合っている。ボリビアが国営主導のモデルを推進する一方で、アルゼンチンでは市場開放が進み、規制の緩い地域ほど企業の進出が活発になっている。
「クリーンリチウム」の調達を目指す取り組みも現れ始めている。トレーサビリティ(追跡可能性)を確保するツールや認証制度もその一例だ。しかし、こうした仕組みは依然として任意にとどまり、実効性のある監督や強制力は伴っていない。
専門家たちは、倫理的なリチウム採掘には先住民との共同管理、透明性の高い合意形成、そして堅牢な環境保護措置が不可欠だと強調する。これらの仕組みがなければ、グリーンエネルギーへの転換は正義や持続可能性を犠牲にして成し遂げられることになるだろう。
リチウムは未来を動かすかもしれない―しかし、本当に作っているのは誰の未来なのか。
世界が電化に向かうなか、マリア・キスペさんのようなコミュニティは、自分たちの存在を「見てもらい、声に耳を傾け、尊重されること」を求めています。
「私たちにも未来があります」と彼女は言う。「でも、その未来が私たちを消してしまうのなら、いりません。」