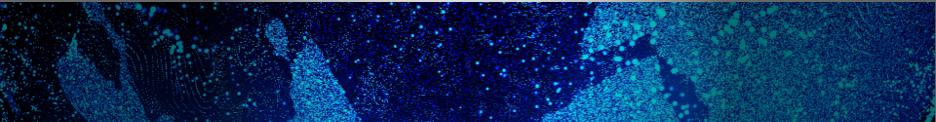国際問題
グラスノスチから沈黙へ:クレムリンはいかにしてロシアのメディア支配を回復したか
かつては脆弱な自由の象徴だったロシアのジャーナリズムは、ウラジミール・プーチン政権下で国家権力の道具となってしまった。
![2000年9月20日、モスクワの作業室でニュース放送の準備を進めるNTV局のスタッフたち。[写真=アレクサンダー・ネメノフ/AFP通信]](/gc7/images/2025/07/02/50958-history_3-370_237.webp)
オリャ・チェピル |
開放の瞬間に、真実が国家の姿を変えてきた。ソビエト連邦の末期には、検閲のない報道の波が国民に新たな国の姿を見せ、政権の崩壊を後押しした。
今日、かつてソ連を揺るがした真実の力が、ウラジミール・プーチン政権下のロシアに挑んでいる。そこでは国家が世論を厳しく統制し、国民が得られる情報を厳しくコントロールしている。
体系的な虚偽情報
ソ連崩壊後も、虚偽情報による工作手法は生き残った。ハーバード大学の人権プログラム「サハロフ・プログラム」の元ディレクター、タチアナ・ヤンケレビッチ氏は、1990年代になってもソ連式の情報操作はロシア国内外で継続していたと指摘している。
彼女の継父であり、物理学者で異見者、ノーベル平和賞受賞者でもあるアンドレイ・サハロフは、ソ連の抑圧やアフガニスタン戦争、そして全体主義体制そのものを強く非難した。
![2023年4月14日、モスクワのアンドレイ・サハロフ博物館・市民センターで職員が箱を運んでいる。[写真=キリル・クドリアフツェフ/AFP通信]](/gc7/images/2025/07/02/50959-history_2-370_237.webp)
サハロフに対する攻勢は、ソ連による虚偽情報工作の象徴的な事例とされている。1980年代には情報機関が忠実なジャーナリストと協力し、国外で彼の信用を失わせるための偽造動画や文書を作成した。
「手紙や動画、書簡などが偽造された。すべてが編集され、さまざまな文脈から切り取られて西側のメディアに流された。目的は金銭ではなく、サハロフを擁護する動きを抑圧することだった」と、ヤンケレビッチ氏はグローバル・ウォッチに語った。
サハロフが追放されていたゴルキー(現ニジニ・ノヴゴロド)では、医師たちがこっそり彼を撮影し、その映像をKGBに渡していた。
「これは単なるプロパガンダではなかった。現実の組織的なすり替えだった」と、ヤンケレビッチ氏は語った。
この工作の狙いは、サハロフを孤立させ、広範な人権運動そのものを沈黙させることにあった。こうした手法はやがて、ソ連崩壊後のプロパガンダ戦略の一部となっていく。
虚偽情報工作は極めて広範囲に及んでいた。これほど明確にソ連のプロパガンダ機関の威力を示す事例は想像しにくい」とヤンケレビッチ氏は語った。
真実がもたらす変革の力
1980年代後半まで、ソ連のメディアは政府の公式見解しか伝えなかった。新聞、テレビ、ラジオはすべて国家の声を代弁し、異論の余地はなかった。
「改革(ペレストロイカ)以前のソ連にはテレビ局が2つしかなく、放送されていたのは『農村時間』や『私はソ連に仕える』といった、眠くなるような番組ばかりだった」と、ベルリン在住のロシア人社会学者・ジャーナリスト、イーゴリ・アイドマン氏はグローバル・ウォッチに語った。彼はロシア政府から「外国エージェント」と指定されている。
その息苦しい状況は、ミハイル・ゴルバチョフ政権下で導入された「グラスノスチ(公開性)」の政策によって変わり始めた。この政策は検閲を緩和し、情報公開を推進するものであった。テレビ番組『ズグリャド(視点)』は、テンポの早い形式で、それまでのソ連型放送スタイルから脱却した。また、かつては堅苦しい挿絵付き週刊誌だった『オゴニョク』も、大胆な政治論評やルポルタージュを掲載し始めるなど、メディアの姿勢が大きく変わっていった。
「ペレストロイカが始まると、検閲は次第に緩和され、やがて完全に撤廃された。それによって扉が開かれ、鋭くて生き生きとした番組に全面的な自由が与えられたのだ」とアイドマン氏は語った。
ソ連市民にとって、初めて異なる視点や、自国の歴史に対する別の解釈に触れることになった。
CNNをはじめとする欧米のニュースメディアは、1991年8月にモスクワで起きたクーデター未遂事件の報道において中心的な役割を果たした。ロシア連邦議会(ホワイトハウス)の外で戦車の上に立つボリス・エリツィンの姿は世界中に瞬時に伝えられ、歴史的な転換点となった。数十年ぶりに、クレムリンが情報の主導権を失った瞬間だった。
「独立した、あるいはそれに近いロシアのジャーナリズムが形成し始め、その中にはテレビ報道も含まれていた」とアイドマン氏は振り返った。
しかし、その真実には代償が伴った。旧体制の崩壊は、経済的混乱、イデオロギーの空白、そして格差の拡大をもたらした。共産主義のエリートは、オリガルヒ(新興財閥)の階級に取って代わられたのである。
「オリガルヒの台頭は、ある種のショック・セラピーに起因している。この“略奪的資本主義”は社会的ダーウィニズムと貧困を生み出した」と、30年以上にわたりロシアとウクライナの関係を研究してきたオーストリア出身の政治アナリスト、グレゴール・ラズモフスキー氏はグローバル・ウォッチに語った。
それは国民のソ連時代からの経済的基盤を崩壊させ、厳しい新たな現実を生み出した。広がる貧困と失業が、突如として富を得た新興エリートと鮮明な対照をなしていたと、ラズモフスキー氏は指摘している。
「バウチャー制度の崩壊によって、一部の狭いエリート層が国有財産を独占する*道が開かれた 」と彼は述べ、広く批判されたソ連経済資産の民営化について言及した。
情報不足にあえぐ市民や、切迫した経済的必要から資金を手放さざるを得なかった市民たちは、ソ連時代の企業が持つ株式をわずかな金額で新興のオリガルヒたちに売り渡してしまった。
「民営化によって、受け取った企業を発展させる経験も意図もない人物が、億万長者や超大富豪になったケースが数多く生まれました」とラズモフスキー氏は述べた。
自由から独占へ
1991年以降、テレビは権力の争点となった。一時的にではあるが、言論の自由も登場した。しかし、やがてオリガルヒたちは影響力獲得のために放送局を次々と買収していった。メディア大物ウラジミール・グジンスキーが率いるNTVは独立した編集方針を貫いた一方で、実業家かつ政界のコネクションを持つボリス・ベレゾフスキーと関係の深いORTは、ジャーナリズムと政権の利害の狭間でバランスを取る姿勢を維持した。
「1990年代には確かに自由が広がったが、メディアは完全に自由だったわけではない。結局、それぞれの支配者のために機能していたのだ」とアイドマン氏は語った。
転機は第一次チェチェン紛争(1994〜96年)の際に訪れた。ロシア国民は破壊された都市や戦死した兵士、抗議する母親たちの映像を目にするようになった。政府系テレビ局でさえも、政権への鋭い批判を放送するようになったのだ。
「当時は国家がテレビを完全に支配していなかった。NTVや独立系ジャーナリストたちは戦争を強く批判していた」とアイドマン氏は語った。
しかし、その開かれた時間はすぐに閉ざされてしまった。2000年を迎える頃には、第二次チェチェン紛争において、ジャーナリストはほとんど戦線への立ち入りを禁じられていた。
「メディアに対する締め付けが始まり、特にプーチンが政権を握るとすぐにNTVを壊滅させたことで、その動きは一層強まった」とアイドマン氏は語った。
プーチンが2000年に政権を握った際、報道の自由の後退が始まり、国家によるメディア支配が強化されていった。
「2000年代以降、ロシアでは国家がテレビを独占するようになった。NTVは壊され、グジンスキーとベレゾフスキーは追放された。残った支配者は、クレムリンだけだ」とアイドマン氏は語った。
「それ以降、表現の自由はほぼ消え失せてしまった」とアイドマン氏は語った。「外国エージェント」を標的にした法律や刑事訴追、検閲によって、ソ連時代の抑圧的な統制が復活している。
「今や残っているのはプーチンに従う人々だけだ。それ以外の人は国外へ出て行ったか、黙りを決め込んでいるかのどちらかだ」とアイドマン氏は語った。
今回は、クレムリンが使える統制手段がさらに増えている。デジタル監視やインターネット検閲、独立メディアの活動禁止、そしてSNSプラットフォームの支配など、こうした新たな抑圧装置が揃っている。
ヤンケレビッチ氏は、政府の行動、特にウクライナにおける行為を犯罪と断じた。
「この件に関わっている人々はもはや人間らしい顔をしていない。しかし、私は誰かを悪魔視したくはない。人を悪魔化すると、その行動を正当化しているかのように受け取られてしまうからだ。でも、私は彼らの行動を正当化したいわけではない。彼らは犯罪者なのだ」と彼女は語った。