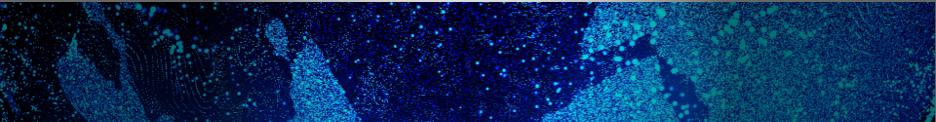国際問題
なぜ世界政治は静的からはほど遠いのか
西側が漂流し、時代遅れの制度にしがみついているという見方は、民主主義体制の柔軟さと強靱さを見落としている。
![インドのナレンドラ・モディ首相(中央)が、2025年9月1日、天津の梅江会展センターで開かれる上海協力機構(SCO)首脳会議を前に、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領(左)、中国の習近平国家主席(右)と語り合う。 [Suo Takekuma/AFP通信]](/gc7/images/2025/09/23/52049-mod-370_237.webp)
Global Watch |
近年、世界政治は変化の乏しい時代に入ったと主張する声が一部にある。そこでは大衆運動が影を潜め、世界はもっぱら少数の強力な指導者の決断によって形作られているという。この見方はしばしば国家主導の言説によって増幅され、西側の衰退と、ロシア・中国・インドといった国々が主体性と主権を掲げて台頭する姿を描き出している。
しかし、この見方は現代の地政学の複雑さを過度に単純化し、世界秩序を形作り続ける理念や制度、人々の活発な相互作用を見落としている。
大衆運動が消え去ったという主張に反して、集団行動は今なお大きな影響力を持っている。平和運動から人権運動まで、大規模な動員は政策の変化を促し、既存の権力構造に挑み続けている。こうした運動は必ずしも革命に直結するわけではないが、未来を形作るうえで、市民の関与が持つ持続的な力を示している。
民主主義国家では、選挙や働きかけ、市民運動を通じて市民が意思決定に影響を及ぼすことができ、その結果、統治は常に説明責任を保ち続ける。専制体制は国民の参加を国家的な優先課題に結びつけていると主張するかもしれないが、それはしばしば個人の自由や異論の犠牲にしている。そうした体制における大衆運動の不在は、安定の証ではなく、抑圧の表れにほかならない。
西側は衰退ではなく適応
漂流する西側が時代遅れの制度にしがみついているという見方は、民主主義体制の柔軟さと強靱さを見落としている。官僚機構は時に遅々として見えることもあるが、透明性・説明責任・協力の枠組みを提供している。欧州連合や国際連合といった制度は、気候変動から紛争解決に至るまで、地球規模の課題に取り組む上で依然として重要な役割を果たしている。
西側の革新力と適応力は、技術、科学、人権分野での主導的役割に顕著に示されている。決して停滞しているわけではなく、西側諸国は再生可能エネルギー、人工知能、グローバル・ヘルスへの投資を通じて未来を積極的に形作っている。西側を受動的な存在として描く見方は、その人々や制度、指導者たちの力強い貢献を考慮していない。
言葉の裏にある現実
ロシアと中国はしばしば攻勢に出る国家として描かれるが、その歩みは決して一様ではない。 ウクライナでの戦争に象徴されるロシアの攻撃的な外交政策は、同国を経済的にも外交的にも孤立させている。ロシアの行動に広範な国民の支持があるという見方は、増大する異論や軍事作戦による人的被害を無視している。
中国の台頭は否定できないが、その中央集権的な統治モデルが直面する課題には、経済の不安定性、人口動態の変化、人権侵害に対する国際的な監視などがある。中国を、主体性を持ち、一枚岩の勢力として描く見方は、長期的安定を脅かす内外の圧力を見過ごしている。
「大きな理念」が世界政治から消え去ったという主張は誤解を招く。自由、平和、革新といった理念は今なお進歩を推し進め、集団的行動を促し続けている。制度も衰退するどころか、多極化した世界の複雑さに対応するために進化している。
国際システムは静的ではなく、国家、指導者、そして人々の相互作用が形作っている。首脳会議や演説が見出しを飾る一方で、実際に世界秩序を規定しているのは、協力、革新、そして強靱さという根底にある力である。
世界政治が単調な時代に入ったという考え方は、現代世界の活力と複雑さを無視している。大衆運動、理念、制度は、指導者たちが統治や外交の課題に取り組んでいる中でも、未来を形作る上で依然として中心的な役割を担っている。
西側は漂流しているのではなく、適応している。ロシア、中国、インドは一枚岩の勢力ではなく、それぞれが内外の圧力に直面している国家である。勢力均衡は固定的な方程式ではなく、主体と理念の活発な相互作用によって成り立っている。